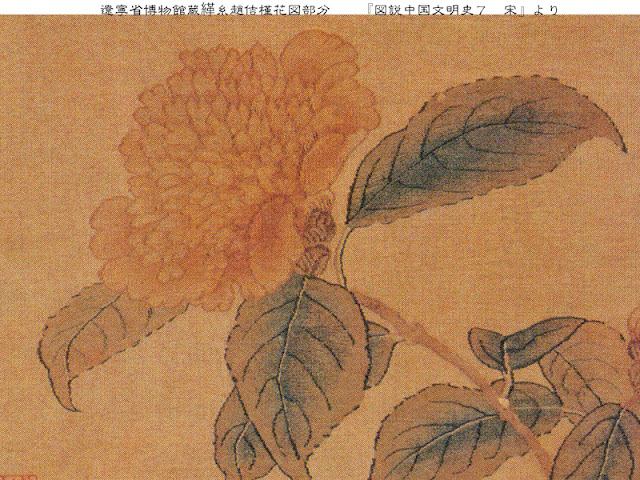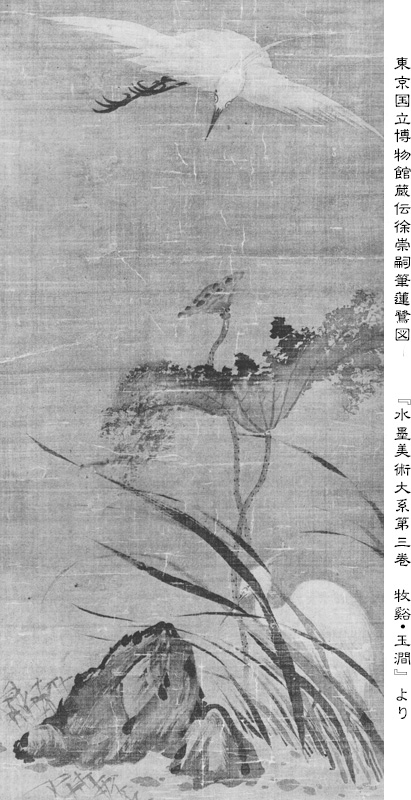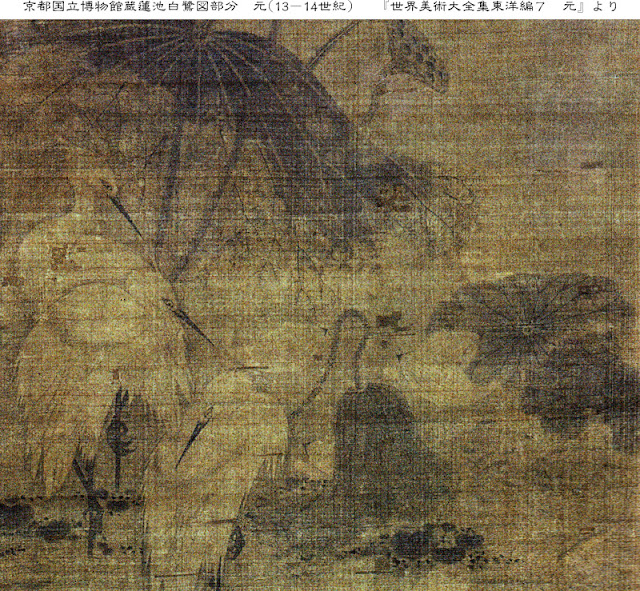徽宗皇帝は水墨画も描いていた。
秋景・冬景山水図 伝徽宗筆 北宋末南宋初 双幅 絹本墨画淡彩 (各)128.0X32.2㎝ 金地院蔵
『水墨美術大系第2巻』は、身延山久遠寺が所蔵する伝胡直夫筆「夏景山水図」や、現在みることができなくなってしまった「春景山水図」とともに元来四季山水図四幅対であったと想像されるという。
各幅には中国の鑑藏印と考えられる「仲明珍玩」「盧氏家蔵」の2印のほか、「天山」の印が押捺されており、かつて3代将軍足利義満の所有であったことを物語っている。もとより能阿弥が筆者を徽宗とした理由、あるいは伝記の全く分らない胡直夫筆の伝称がつけられた時期もその根拠も明白ではないという。
日本でのみ「伝徽宗筆」とされているらしい。
北宋末の多様な山水画風の全てを明確化しえない現在、この作品の北南宋交替期説を覆す決定的な理由づけは不可能といえるが、筆墨技法の問題よりも空間表現や画中人物の意味等の追求がむしろ重要ではないかと考えられる。
ことに「秋景山水図」にみる対角線構図、樹根によって舞鶴をみる人物の視線、大きな近景の土坡を通してはるか下方にまで空の拡りを暗示する構図法などは、南宋中頃、対角線構図法の完成後の作品を思わせる。
また「冬景図」におけるあまりに近接視した景境の把え方、左上方より斜下方に懸崖をおきながら下辺を完全に余白とする方法、左方の大きな岩と右上方の懸崖、画中人物が立つ山路の展開の方向等、梁楷筆「雪景山水図」と似た構図形式が認められる。
また両幅に点苔が多用されている点を山水画史上の点苔の発展過程の中で解釈するなら、12、3世紀の交を中心とする時期の作品とした方がよいように思われる。いずれにしても、馬・夏の亜流による形式化した院体山水画に比べるなら技法的にも画品の上でもはるかにすぐれた作品であることは間違いないという。
末尾の馬・夏は馬遠・夏珪のこと。
徽宗は自らが登場する図も描いていたらしい。
聴琴図 伝徽宗筆 147.2X51.4㎝ 北京・故宮博物院蔵
『図説中国文明史7 宋』は、画中の徽宗は道士の服を着用し、2人の士大夫の前で琴を弾いており、文人の雅な趣に富んでいる。そこには、文治および道教に対する、徽宗の尊崇の念が表現されている。また、道教を信奉したことから、「教主道君皇帝(道教の一派である神霄派の道士林霊素は、徽宗が天の上帝の長男である長生大帝君の生まれ変わりでありと説いたことにちなむ)」とみずから称したこともあるという。
『図説中国文明史7 宋』は、画中の徽宗は道士の服を着用し、2人の士大夫の前で琴を弾いており、文人の雅な趣に富んでいる。そこには、文治および道教に対する、徽宗の尊崇の念が表現されている。また、道教を信奉したことから、「教主道君皇帝(道教の一派である神霄派の道士林霊素は、徽宗が天の上帝の長男である長生大帝君の生まれ変わりでありと説いたことにちなむ)」とみずから称したこともあるという。
右上は蔡京の七言絶句で、徽宗が創り出した痩金体で書かれている。
小さな図版なので、徽宗の顔がよくわからないのが残念。
 |
| 北京故宮博物院蔵伝徽宗筆聴琴図 北宋 『図説中国文明史7 宋』より |
搗練図巻 張萓筆(唐代) 徽宗模 北宋・12世紀前半 絹本着色 37.0X145.3㎝ ボストン美術館蔵
『世界美術大全集東洋編5』で井手誠之輔氏は、本画巻は、宮廷の仕女がそれぞれ砧の上に絹布を載せ、木槌で打ち柔らげて光沢を出している場面、絹布を裁断する場面、長く広げられた白絹に火熨斗を当てて絹布の皺をのばす場面を一図の中に収め、絹布を制作する作業工程を表した作品である。中には団扇で炭火をあおぐ童女や白絹を持って火熨斗を当てる手伝いをする童女らのほか、まだあどけない童女が、広げられた白絹の下で遊び回るようすなどが描かれ、平穏な宮廷生活を偲ばせる設定となっているという。
日本の絵巻でも、物語の進行とは全く関係のない人々の普段の生活の様子が描かれていたりして、それで当時の人々の暮らしをうかがい知ることができて、貴重な史料という一面もある。
この図の複数の童女は見習いだろうか、それとも宮廷の士女の子供たちだろうか。まさか公主ではないだろう。
本画巻の巻頭には、金の章宗(在位1189-1208)が北宋末の徽宗皇帝の痩金体に倣って書いた「天水墓張萱搗練図」の題記があり、さらに題記上の「明昌」印をはじめ、画巻の各所に章宗の明昌御璽7題が捺されていて、金の内府に収蔵されていたことを伝えている。「天水」とは徽宗のことで、本画巻が、金の章宗のころ、徽宗が唐の張萱の描いた搗練図を模写した作品として認識されていたことがわかる。
徽宗が模写したという張萱は、唐代を代表する宮廷仕女図の作者である。徽宗の宣和コレクションを著録した『宣和画譜』巻5には、47点の張萓の作品があり、その中に、本画巻の原本となった可能性を持つ「搗練図」が見える。
本画巻には、ふっくらと肥満した女性の姿態や、額の中央に花鈿をあしらう化粧などに、唐代仕女図の感化が認められるが、無背景を基本とする中に必要最低限のモティーフを配する構成や、人物の姿態を正面・側面・背面など、自在に変化させながら、奥深い空間を暗示する手法には、「韓熙載夜宴図巻」とも共通する特色が見られ、原画にかなりの再構成を加減したことが想像される。
無款の本画巻の制作者について、徽宗筆の伝承を否定する材料はない。しかしながら、徽宗門下には、「千里江山図巻」を描いた王希孟のような優れた画学生も輩出したようで、徽宗の真筆か、あるいは、画学生によるその模写か、にわかに決しがたい。すぐれた構想をはじめ、仕女の服装の細部にわたる精細な意匠や質感表現には、類まれな力量がうかがわれ、徽宗の強い影響下で本画巻が制作されたことに変わりはない。徽宗周辺で、張萓の作品を参照した例として、「虢国夫人遊春図」(遼寧省博物館)も知られているという。
全員が柄の細かな薄い衣服を着ている。張萓の図を模しているというが、服装は唐代のものではない。おそらく宋代のものだろう。
『図説中国文明史7』は、宋代において、紡績業のなかでも絹織物業の発展には目を見張るものがありました。養蚕業と絹織物業は専業化に向かい、絹織物製品を専門に生産する「機戸(機織屋)」と「機坊(機織工房)」が登場しました。こうして絹織物の生産量は大幅に増え、その材質も唐代や元代にくらべてすぐれていました。麻布と綿布の生産量は伸び、なかでも綿織物業は日増しに普及していった新興の手工業でしたという。
婦人も子供も小さな文様を織り込んだ薄手の絹布を着ている。
 |
| ボストン美術館蔵徽宗模張萓筆搗練図巻部分 北宋・12世紀前半 『世界美術大全集東洋編5』より |
さて、このような絵画を描いた徽宗皇帝とは。
『図説中国文明史7 宋』は、徽宗は典型的な文人であり、当時名の聞こえた画家であり、また書家でもありました。徽宗の院体花鳥画とその独創的な「痩金体」の書法は、中国の芸術史において高い地位を有しています。宋代の皇帝のなかで、徽宗ほど文化的功績を残したものはいません。
宋代の土大夫は、別荘に大きな園林を設け、そこに水をひいて池を掘り、草花や竹や木を植えました。さらに仮山(築山)を築くことで彩りを添え、これによって山水を尚び風雅を愛する文人の興趣を具現しました。
徽宗は、ことに江南の珍しい花や奇石を愛でたので、それらを江南から都に運ばせ皇宮の園林に配しました。その運搬には多くの人手を要したばかりでなく、役人の汚職も加わり、ついに方臘の乱(宣和2年 1120)などの大規模な民衆の蜂起が起こりました。
徽宗が北宋滅亡の元凶となった理由は、おもに政治面での智謀が、文学や芸術面での才能にはるかに及ばなかったからです。
異民族の女真族の王朝である金軍と連合して、同じく異民族の王朝の遼を滅ぼしました。
こうして宋朝は、五代後晋が遼に割譲した燕雲十六州(北京、大同を中心とした河北、山西一帯)をとりもどしたものの、金軍に宋朝の軟弱さと無能さを露呈することになりました。宣和7年(1125)に金軍は南下して宋を侵略し、文弱な徽宗は、皇位を急いで子の欽宗に譲りました。靖康2年(1127)北宋は滅亡し、徽宗と欽宗は、金軍に囚われて五国城(現在の黒龍江省依蘭県にある)に幽閉され(靖康)、ついに他郷で命絶えることになりましたという。
周囲に異民族の国々が犇めいている中で、徽宗皇帝は優雅に絵を描いたり、書をしたためたり、それだけでなく書作品や絵画作品を系統的に記録するなどということをしていて国を滅ぼしてしまった。
参考文献
「世界美術大全集東洋編5 五代・北宋・遼・西夏」 小川裕充・弓場紀知 1998年 小学館
「世界美術大全集東洋編6 南宋」 嶋田英誠・中澤富士雄 2000年 小学館
「よみがえる川崎美術館 川崎正藏が守り伝えた美への招待展図録」 2022年 神戸市立博物館
「水墨美術大系第2巻 李唐・馬遠・夏珪」 鈴木敬 1978年 講談社
「図説中国文明史7 宋 成熟する文明」 稲畑耕一郎監修 2006年 創元社