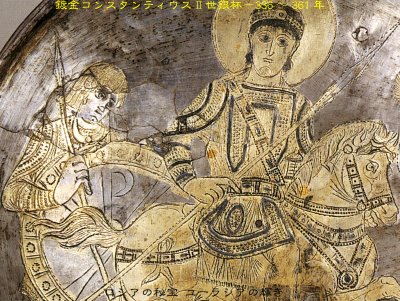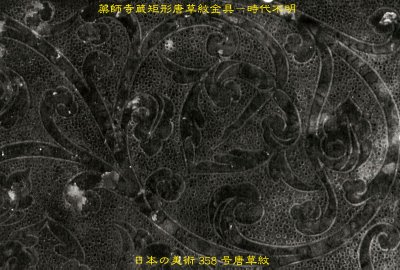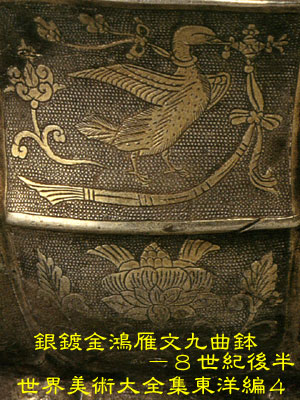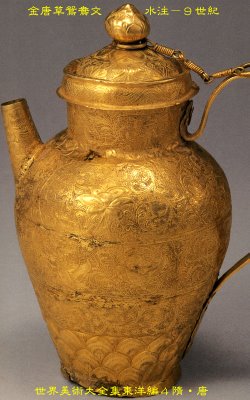正倉院展ではラクダによく出会う。去年の正倉院展で見た駱駝はとても小さなものだった。花の咲く野に遊ぶ鳥、野を駆ける獅子や鹿、鹿を追いかける鳥グリフィン、象に乗ってポロをする人や、飛びかかる獅子に象の上から矢で狙う人、鳥グリフィンに乗ってポロをする人などに交じって、駱駝や駱駝を引く人などが、「象牙を切り抜き線刻をし淡彩をほどこし」て表されている。
同展図録は、宝庫のシタン製木画の器物は、洗練された表現技法に共通する要素が多く、おそらく直接唐朝廷が関わったことを想像させる。なお、トルファン・アスターナ古墓からは小型の棊局や囲碁に興ずる仕女を描いた絹絵が出土している。盛唐の文化が東西に及んだ一例を知ることができるという。
文中のアスターナ185墓出土の「美人囲碁図」(8世紀)は、「シルクロード 絹と黄金の道展」で見た。その碁盤は格狭間(こうざま、脚部の刳り)が3つあり、側面に木画がない分低い。同展では206墓出土の「碁盤」(7世紀)も展観されていた。こちらは小型の模型と説明にあるが、明器(実用品ではなく、副葬用に作られたもの)だろう。格狭間は2つで、単純な刳りである。
 木画紫檀棊局に表された駱駝はフタコブラクダである。別々の面にあるものを縦に並べてみたら、物語になった。野でくつろぐラクダたち。そこにラクダ使いがやってきて、捕まえるタイミングを図っている。茶色いラクダの方が御しやすそうだ。茶色い方に縄をかけて引っ張ると、茶色い方は緑のラクダに助けを求めるが、緑の方は素知らぬ顔で草をはんでいる。しかし、とうとう緑のラクダも縄を掛けられ、ラクダ使いは手こずった緑の方を引き、もう1人のラクダ使いは茶色い方を縄を掛けずに連れていくことにした。
木画紫檀棊局に表された駱駝はフタコブラクダである。別々の面にあるものを縦に並べてみたら、物語になった。野でくつろぐラクダたち。そこにラクダ使いがやってきて、捕まえるタイミングを図っている。茶色いラクダの方が御しやすそうだ。茶色い方に縄をかけて引っ張ると、茶色い方は緑のラクダに助けを求めるが、緑の方は素知らぬ顔で草をはんでいる。しかし、とうとう緑のラクダも縄を掛けられ、ラクダ使いは手こずった緑の方を引き、もう1人のラクダ使いは茶色い方を縄を掛けずに連れていくことにした。そう言えば、昨夏クチャ郊外を車で移動していて、ラクダを時々見かけた。ガイドの丁さんが「野生のラクダは人を見ると逃げますが、放牧しているラクダは逃げません」と言っていた。だから、このラクダは輸送用に訓練されたラクダか、放牧しているラクダだろう。

一昨年正倉院展でみた駱駝は去年のものよりは大きかった、と思って四弦琵琶をじっくり見ると、ラクダではなく象だった。なんとええ加減な記憶だろう。
捍撥(かんぱち)には皮を張り白地下地に彩絵を施した上にその保護のために油を引く。密蛇絵(みちだえ)の一種である。縦約40cm、横約16cmの小さい画面に、縦方向に近景から遠景まで・略・奥行きのある図様を作り、盛唐期山水画を彷彿させる。図は騎象奏楽図と通称され、唐朝にもてはやされた異国趣味あふれるもの。・略・
なお、白色顔料の一部からは、純正鉛白ではなく塩化物系化合物が検出され、わが国における製作とみる有力な根拠とされるという。
そう言えば、成分分析でこの四弦琵琶が日本製であることがこの年に発表されたのだった。
 正倉院の宝物で最も有名なものの1つが五弦琵琶だと思う。なにしろ世界唯一の五弦琵琶の遺品なのだから。その唯一の五弦琵琶に螺鈿で表されたものはフタコブラクダに乗る楽人だ。そして、この楽人が奏でているのは四弦琵琶なのだ。
正倉院の宝物で最も有名なものの1つが五弦琵琶だと思う。なにしろ世界唯一の五弦琵琶の遺品なのだから。その唯一の五弦琵琶に螺鈿で表されたものはフタコブラクダに乗る楽人だ。そして、この楽人が奏でているのは四弦琵琶なのだ。  このように昔の正倉院展の図録などを調べていて、私はこの五弦琵琶を見ていないことに気付いた。五弦琵琶が描かれているキジル石窟のガイド馬さんに「五弦琵琶を見たことがありますか」と聞かれ、確信を持って「あります」と言ったのだが。また馬さんは質問した「正倉院展では正倉院の宝物が全部見られますか?」「いえ、見られません。正倉院の宝物は数が多いので、毎年数十点公開されるだけなので、全部見ようと思ったら、何十年もかかります」そう答えると若い馬さんはがっかりした様子だった。
このように昔の正倉院展の図録などを調べていて、私はこの五弦琵琶を見ていないことに気付いた。五弦琵琶が描かれているキジル石窟のガイド馬さんに「五弦琵琶を見たことがありますか」と聞かれ、確信を持って「あります」と言ったのだが。また馬さんは質問した「正倉院展では正倉院の宝物が全部見られますか?」「いえ、見られません。正倉院の宝物は数が多いので、毎年数十点公開されるだけなので、全部見ようと思ったら、何十年もかかります」そう答えると若い馬さんはがっかりした様子だった。五弦琵琶が展観されてからかなりの歳月がたったように思う。そろそろ来年あたり、見てみたいなあ。
※四弦琵琶と五弦琵琶の画像は五弦琵琶は敦煌莫高窟にもあったにあります
※参考文献
「太陽正倉院シリーズ1 正倉院とシルクロード」 1981年 平凡社
「第五十六回正倉院展図録」 2004年 奈良国立博物館
「第五十七回正倉院展図録」 2005年 奈良国立博物館